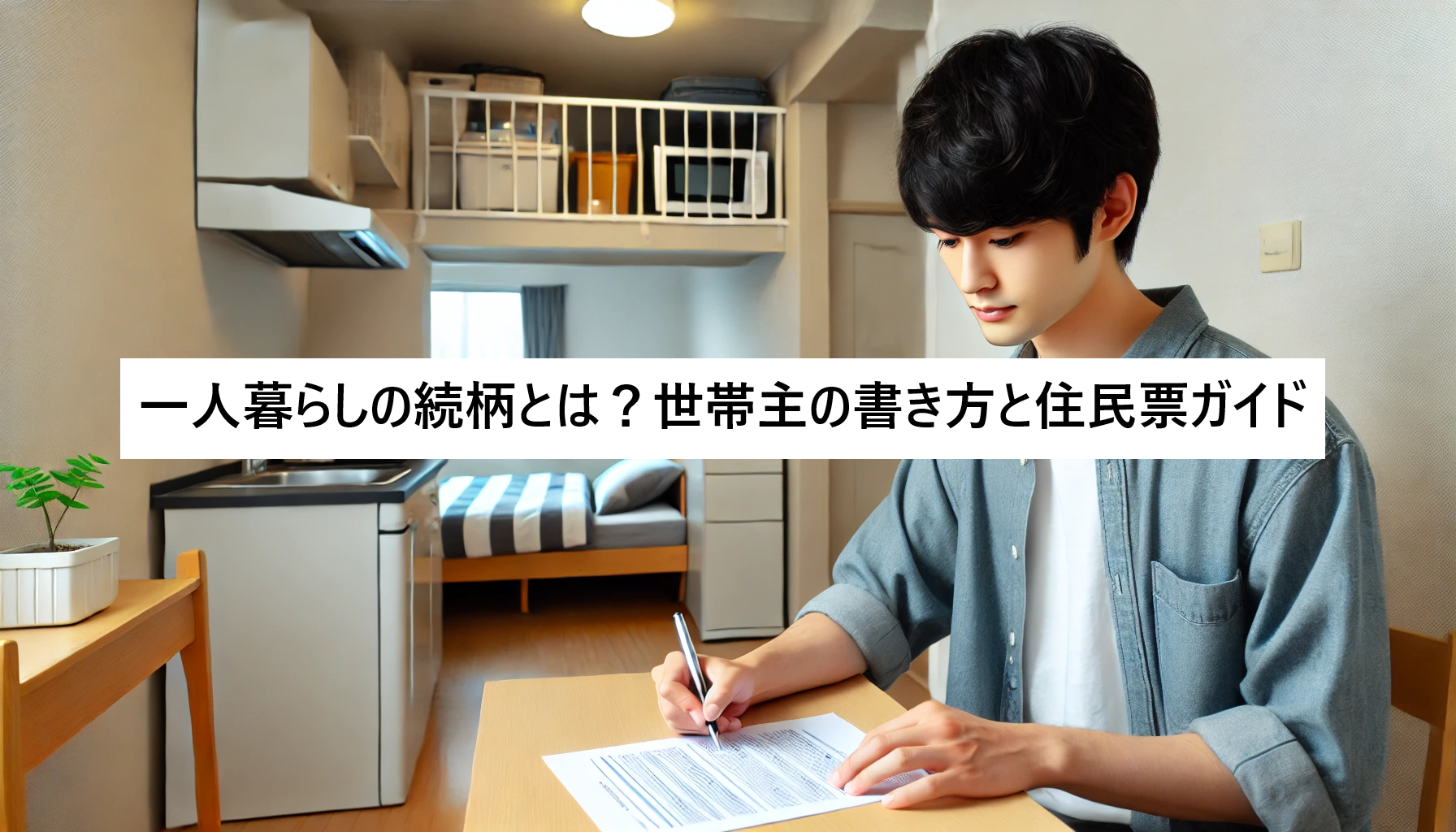一人暮らしを始めると、賃貸契約や役所の手続き、年末調整などで「世帯主」や「続柄」を記載する場面に直面します。
実家暮らしの時は意識しなかったため、「一人暮らしの場合、世帯主は誰になるの?」「続柄とはどう書けばいい?」と戸惑う方も多いでしょう。
特に大学生の場合、親の扶養に入っているとさらに複雑に感じがちです。
また、世帯主との続柄の書き方は、住民票を移しているかどうかで大きく変わります。
例えば、住民票移してない状態だと実家の世帯主が基準になりますし、仮に同棲していて世帯主との続柄が妻の場合など、パターンによって記載方法が異なります。
一人暮らしをしたら何世帯として扱われるのか、そして世帯主の届出や、賃貸契約・年末調整での続柄の書き方について、基本的なルールを理解しておくことが重要です。
この記事では、一人暮らしの続柄に関する疑問を解消し、世帯主の定義から具体的な書類の書き方までを分かりやすく解説します。
- 一人暮らしの「世帯主」が誰になるのかが分かる
- 住民票の状況に応じた「続柄」の正しい書き方が分かる
- 賃貸契約や年末調整など場面別の記載例が分かる
- 世帯主になるメリットや注意点が分かる
一人暮らしで知るべき続柄の基本

- そもそも続柄とはどういう意味?
- 一人暮らしをしたら何世帯になる?
- 大学生の一人暮らしでも本人が世帯主
- 世帯主は誰?住民票移してない場合
- 自分が世帯主のときの続柄は「本人」
そもそも続柄とはどういう意味?
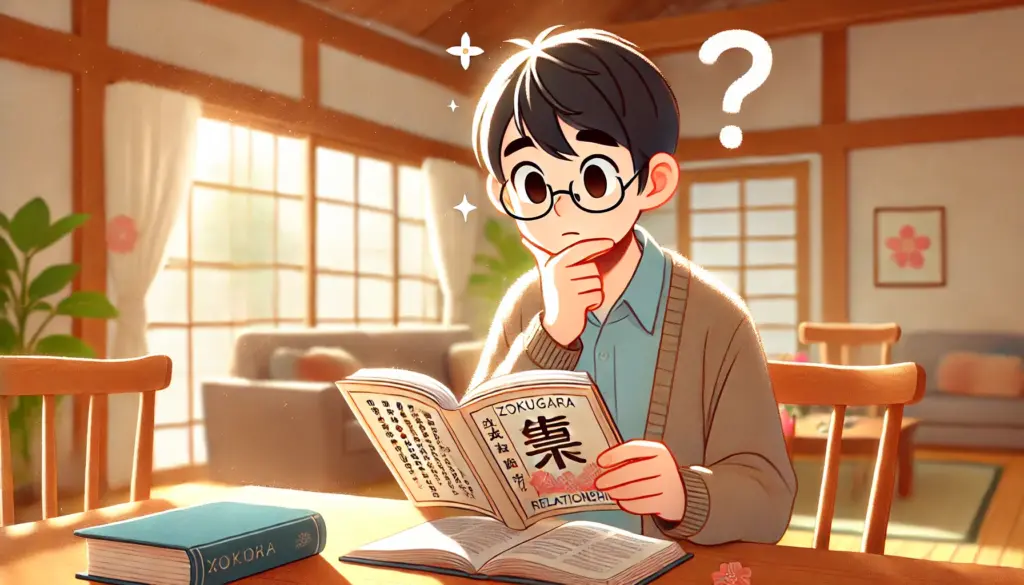
「続柄」とは、その世帯の「世帯主」から見た関係性を示す言葉です。
正しくは「つづきがら」と読みますが、一般的に「ぞくがら」という読み方も浸透しています。
公的な書類や手続きにおいて、世帯の構成を明確にするために使用されます。例えば、世帯主が父親である場合、その子供の続柄は「子」となり、妻の続柄は「妻」となります。
あくまで住民票に記載された世帯主を基準にした関係性を指すため、誰が世帯主なのかを正確に把握しておくことが、続柄を正しく記載する第一歩となります。
一人暮らしをしたら何世帯になる?
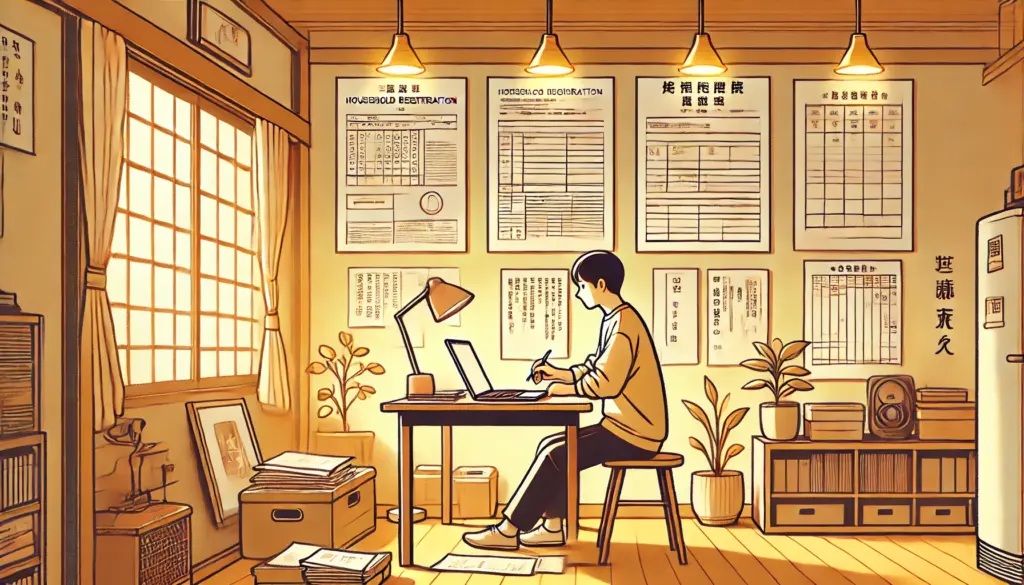
一人暮らしを始め、新しい住所に住民票を移した場合、法律上は「1世帯」として扱われます。
法律(住民基本台帳法)における「世帯」とは、「住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者」と定義されています。
つまり、家族で暮らしている場合だけでなく、一人で独立して生計を立てている人(単身者)も、それ自体で一つの独立した世帯として認められるのです。
このため、一人暮らしで住民票を移すと、実家の世帯とは別の新しい世帯が作られることになります。
大学生の一人暮らしでも本人が世帯主

「大学生だから親の扶養に入っているし、世帯主は親のままなのでは?」と考える方も多いですが、これは誤解です。
大学生であっても、一人暮らしのために住民票を移せば、その本人が新しい世帯の「世帯主」となります。
世帯主になるかどうかは、年齢(15歳以上であれば可)、職業、収入の有無、扶養に入っているかどうかには関係ありません。
あくまで「住民票」を基準に判断されます。親からの仕送りで生計を立てている場合でも、住民票が別(=独立した住居)であれば、法的には別世帯の世帯主として登録されます。
世帯主は誰?住民票移してない場合

一人暮らしを始めても、住民票を実家から移していない場合、あなたの「世帯主」は実家の世帯主(多くの場合、父親か母親)のままです。
住民票を移していないということは、法律上は「実家の世帯に属したまま、別の場所に一時的に滞在している」という扱いになります。
そのため、あなた自身の独立した世帯は存在しないことになります。
この場合、年末調整やその他の公的書類で「世帯主の氏名」を問われたら、実家の世帯主の氏名を記載し、「世帯主との続柄」は、その世帯主から見たあなたの関係(例:父が世帯主なら「子」)を記載する必要があります。
住民票を移さない場合の注意点
住民票を移さないと、法律(住民基本台帳法)で定められた義務に違反する可能性があるだけでなく、以下のようなデメリットが生じます。
- 現住所での選挙権が行使できない
- 運転免許証の更新手続きが旧住所の管轄になる
- 現住所の役所で公的な証明書(住民票の写しなど)が発行できない
- 会社の住宅手当などが受けられない場合がある
特別な理由がない限り、引っ越しから14日以内に住民票を移す(転入届を出す)手続きを行いましょう。
自分が世帯主のときの続柄は「本人」
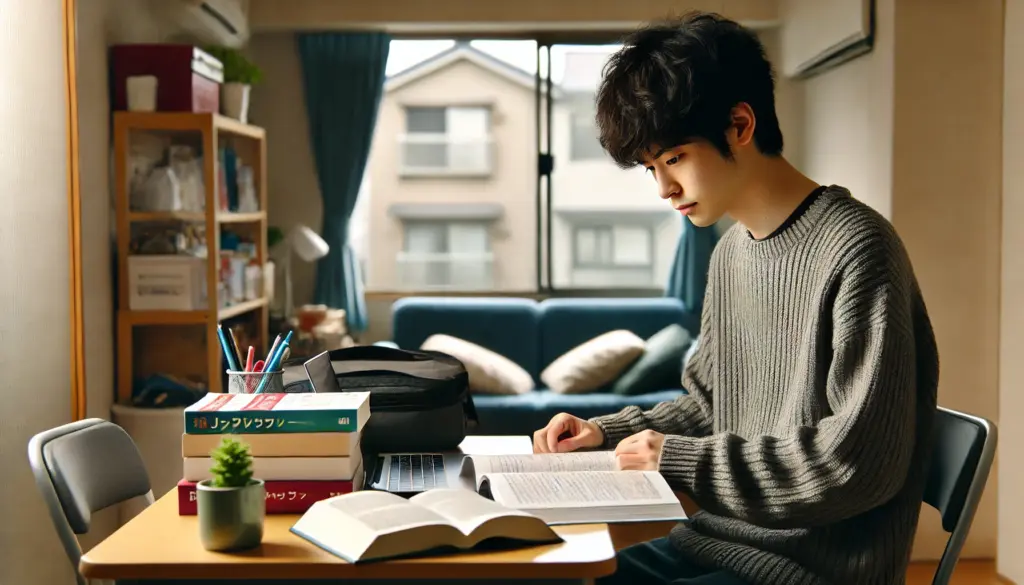
一人暮らしで住民票を正しく移した場合、あなた自身が世帯主となります。
この場合、書類の「世帯主との続柄」欄には「本人」または「世帯主」と記載するのが正解です。
なぜなら、その世帯を構成しているのはあなた一人だけだからです。世帯主=あなた自身であるため、世帯主から見た関係性は「本人」以外にありません。
賃貸契約書や年末調整の書類などで続柄の記載に迷ったら、住民票を移していれば「本人」と覚えておけば間違いありません。
ケース別・一人暮らしの続柄の書き方

- 世帯主との続柄が妻の場合の書き方
- 世帯主の届出・賃貸・年末調整の続柄
- 世帯主になるメリットと注意点
- 世帯主を変更する手続きと必要なもの
- 実家暮らしでもできる世帯分離とは?
- まとめ:一人暮らしの続柄は住民票が鍵
世帯主との続柄が妻の場合の書き方
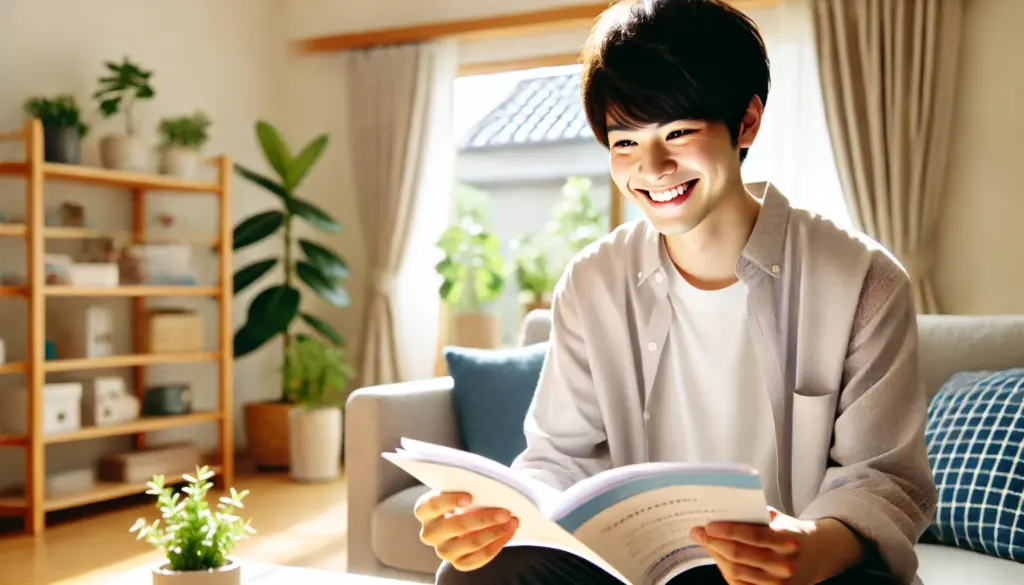
一人暮らしのテーマとは少し異なりますが、公的書類の書き方として「世帯主との続柄が妻の場合」についても解説します。
これは、同棲や結婚などで二人以上の世帯になる場合のパターンです。
書き方は、住民票上の世帯主が誰になっているかで決まります。
- 世帯主が「夫」の場合
妻が書類を記入する際、「世帯主の氏名」には夫の名前を書き、「世帯主との続柄」欄には「妻」と記載します。
- 世帯主が「妻(本人)」の場合
共働きなどで、妻が世帯主として住民票に登録されている場合、「世帯主の氏名」には自分の名前を書き、「世帯主との続柄」欄には「本人」と記載します。
どちらを世帯主にするかは、生計を主に支えている方で登録するのが一般的ですが、法律上の決まりはないため、どちらでも構いません。
役所への届出内容が基準となります。
世帯主の届出・賃貸・年末調整の続柄
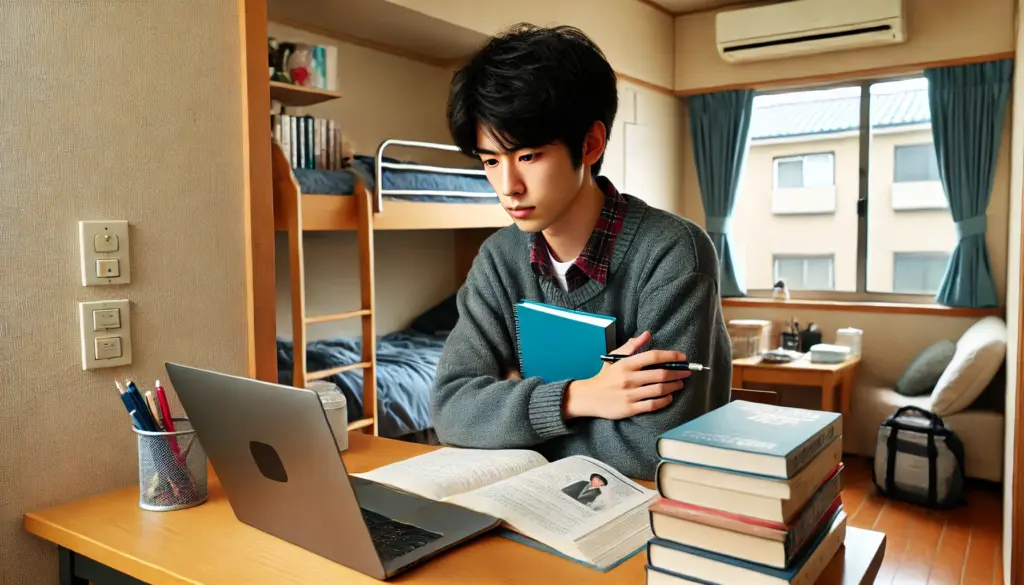
一人暮らしを始めると、さまざまな場面で世帯主や続柄の記載が求められます。
ここでは代表的な3つのケースについて、手続きと書き方を解説します。
世帯主の変更(転入届・転出届)
一人暮らしで自分が世帯主になるための最初の手続きが、住民票の異動(引っ越し)です。
- 転出届の提出
まず、これまで住んでいた(実家など)市区町村の役所で「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。
- 転入届の提出
次に、引っ越し先の新しい市区町村の役所に、引っ越した日から14日以内に「転出証明書」と本人確認書類などを持参し、「転入届」を提出します。
この転入届を提出する際に、新しい世帯の「世帯主」として自分自身を登録します。
これにより、正式にあなたが世帯主となります。
賃貸契約書での続柄
賃貸物件の契約書にも、世帯主や続柄を記載する欄があります。これも住民票の状況によって変わります。
- 住民票を移す(自分が世帯主になる)場合
世帯主の氏名:自分の氏名
続柄:本人
- 住民票を移さない(実家の世帯のまま)場合
世帯主の氏名:実家の世帯主の氏名(例:父親の氏名)
続柄:世帯主から見た関係(例:子)
不動産会社によっては、契約者の親を世帯主とするよう指示されるケースもありますが、基本は住民票の登録状況に従って記載します。
年末調整(扶養控除等申告書)の続柄
アルバイト先や会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にも世帯主を記載する欄があります。
この書類には「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」という欄があります。
一人暮らしで自分が世帯主の場合
- 世帯主の氏名:自分の氏名
- あなたとの続柄:本人
住民票を移しておらず、実家の父が世帯主の場合
- 世帯主の氏名:父親の氏名
- あなたとの続柄:父
年末調整の書類は「申告者(あなた)から見た続柄」を書く欄(例:扶養親族の続柄)と、「世帯主」について書く欄が混在しています。
書類の様式をよく確認し、「世帯主」の欄には住民票上の世帯主の情報を書くと覚えておきましょう。
世帯主になるメリットと注意点

一人暮らしで世帯主になることには、メリットと注意点の両方があります。
両方を理解した上で手続きを進めましょう。
世帯主になるメリット
- 会社の住宅手当(家賃補助)の対象になる
多くの企業では、住宅手当の支給条件を「世帯主であること」としています。
世帯主になることで、毎月の家賃負担を軽減できる可能性があります。
- 公的手続きがスムーズになる
住民票の写しや印鑑証明書など、公的な証明書が必要になった際に、現住所の役所ですぐに発行できます。
- 行政サービスの利用
住んでいる地域の選挙権が行使できるほか、図書館や公共施設などの行政サービスを正規の住民として利用できます。
世帯主になる際の注意点
- 親の税金(扶養控除)に影響が出る可能性
これは世帯主になることの直接的な影響ではありませんが、あなたのアルバイト収入などが一定額(年間103万円など)を超えると、親の税法上の「扶養親族」から外れます。
その結果、親が納める税金が高くなる可能性があります。
- 国民健康保険料の支払い義務
これまで親の健康保険(社会保険)の被扶養者だった場合でも、あなたの収入が年間130万円を超えると、扶養から外れます。
その場合、自分で国民健康保険に加入し、保険料を納付するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
特に扶養に関しては、世帯主になるタイミングで親とよく相談しておくことが大切です。
世帯主を変更する手続きと必要なもの

「世帯主の変更」には、2つのパターンがあります。
- 引っ越し(転入)に伴い、新しく自分が世帯主になる
- すでに住んでいる世帯で、世帯主を別の人に変更する
ここでは、2のパターン(例:同棲していた相手が引っ越し、残った自分が世帯主になる場合や、実家で親から子へ世帯主を変更する場合)について解説します。
この手続きを「世帯主変更届」と言います。
世帯主変更届の手続き
- 届出場所:現在住んでいる市区町村の役所・役場
- 届出期間:変更があった日(世帯主が死亡、転出などした日)から14日以内
- 届出できる人:新しい世帯主、または同じ世帯の人(代理人の場合は委任状が必要)
- 必要なもの:
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(自治体により不要な場合あり)
- 国民健康保険証(加入している世帯の場合)
正当な理由なく14日以内に届け出ないと、過料(罰金)が科される場合があるため注意しましょう。
実家暮らしでもできる世帯分離とは?
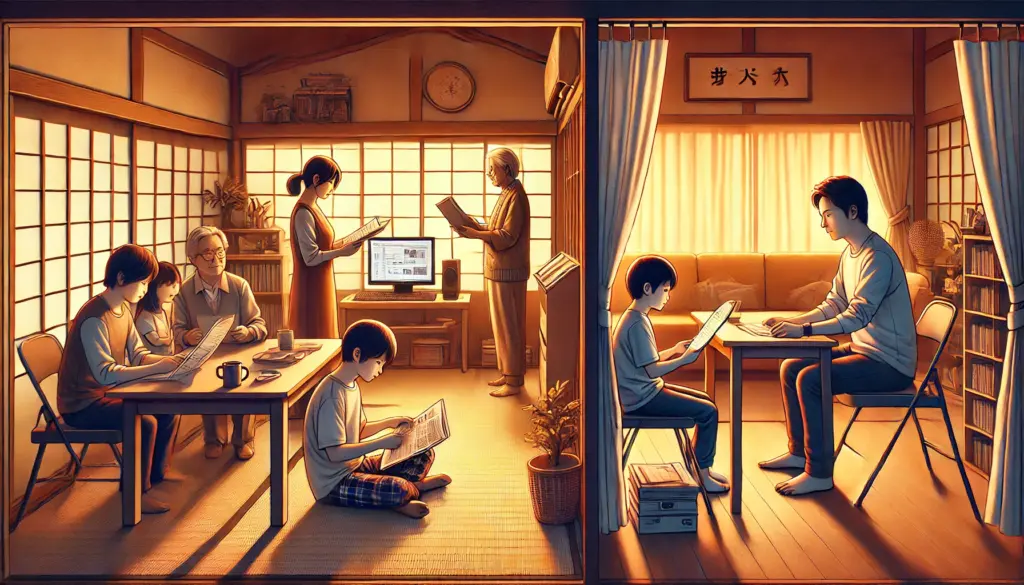
最後に、世帯を理解する上で重要な「世帯分離」について触れておきます。
これは、同じ家に同居しながら、住民票上の世帯を複数に分けることを指します。
例えば、実家で親(世帯主)と同居している社会人の子供が、生計を別にしている場合、「世帯分離届」を提出することで、親の世帯とは別の「子供自身が世帯主の世帯」を作ることができます。
この場合、一つの住所に2つの世帯が存在することになります。
世帯分離の主なメリットは、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの負担額が変わる可能性があることです。
これらの保険料は「世帯の所得」を基準に計算されるため、所得の高い子供世帯と分離することで、親世帯の保険料負担が軽減される場合があります。
一方で、扶養から外れる、家族手当の対象外になる、住民票などを家族が代理で取得しにくくなる、といったデメリットも考慮する必要があります。
まとめ:一人暮らしの続柄は住民票が鍵

一人暮らしの続柄や世帯主に関する疑問点について、要点を以下にまとめます。
- 続柄とは「世帯主から見た関係性」のこと
- 一人暮らしで住民票を移せば、自分が世帯主の「1世帯」になる
- 世帯主は年齢や収入、職業(大学生など)に関係なく決まる
- 住民票を移していれば、大学生でも本人が世帯主になる
- 住民票を移していない場合、世帯主は実家の世帯主(親など)のまま
- 自分が世帯主の場合、続柄の書き方は「本人」
- 世帯主との続柄が妻の場合、世帯主が夫なら「妻」、自分なら「本人」
- 世帯主になるには、引っ越し時に「転入届」で自分を世帯主として登録する
- 賃貸契約書の続柄も、住民票を移していれば「本人」
- 年末調整の書類では「世帯主の氏名」と「あなたとの続柄」を記載する
- 世帯主になるメリットは、会社の住宅手当が受けられる場合があること
- 注意点として、親の扶養から外れると親の税金に影響が出ることがある
- すでに住んでいる世帯で代表者を変える手続きは「世帯主変更届」
- 手続きは変更から14日以内に役所で行う
- 同じ家に住みながら世帯を分ける「世帯分離」という手続きもある